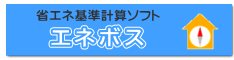省エネ基準の計算方法が2021年4月から変更になりました。
そのため外皮平均熱貫流率(UA値)、平均日射熱取得率(ηA値)の計算方法などが一部変更になっています。
なお、旧計算法は経過措置として2022年3月まで使用することができます。
主な変更点は以下の通りです。
外皮平均熱貫流率(UA値)
熱貫流率
面積比率法
以下の面積比率法の表が削除されました。
・軸組構法において柱・間柱間に断熱し付加断熱する場合の外壁の面積比率
・枠組壁工法においてたて枠間に断熱し付加断熱する場合の外壁の面積比率
・木造においてたるき間に断熱し付加断熱(横下地)する場合の屋根の面積比率
熱貫流率補正法(簡略計算方法)
簡易な熱貫流率の計算方法である熱貫流率補正法が削除されました。
欄間付きドア、袖付きドア等のドアや窓が同一枠内で併設される場合の開口部の熱貫流率
欄間付きドア、袖付きドア等のドアや窓が同一枠内で併設される場合の開口部の計算式が追加されました。
窓・ドアの熱貫流率
省エネ基準のテキストで仕様別の窓・ドアの熱貫流率一覧が変更になりました。
土間床・基礎断熱の計算方法
基礎断熱・土間床の計算方法が変更になりました。
まず、基礎壁と土間床外周部を分けて計算します。
基礎壁は基本的には外壁などと同様に計算します。
基礎のコンクリートと厚さから熱貫流率を計算します。
基礎断熱している場合は、コンクリートと断熱材の熱抵抗計を計算して熱貫流率を計算します。
基礎壁の面積は外皮面積に加算します。
土間床外周部は以下の計算方法があります。
・基礎形状によらない値を用いる方法
・代表的な仕様の計算表を用いる方法
基礎形状によらない値を用いる方法は簡易な計算なため安全側で計算され、基準をクリアしづらくなります。
代表的な仕様の計算表を用いる方法は、省エネ基準で用意されている条件に当てはまる仕様のみのため、いろいろな仕様に対応することはできません。
厳密に言いますと、定常二次元伝熱計算により算出する方法もありますが、計算や設定が複雑なためあまり一般的ではありません。
なお、当面の間は従来の計算方法を用いることができます。
(土間床・基礎断熱の旧計算方法は現在のところ期限は設けられていません)
従来の計算方法は様々な仕様に対応することができますし、省エネに計算される傾向がありますので、当面は従来の計算方法が有利なのではないかと思います。
(住宅の条件にもよります)
平均日射熱取得率(ηA値)
日射熱取得率
欄間付きドアや袖付きドア等のドアや窓が同一枠内で併設される場合の開口部の日射熱取得率
欄間付きドア、袖付きドア等のドアや窓が同一枠内で併設される場合の開口部の計算式が追加されました。
土間床・基礎断熱の計算方法
従来の計算方法では基礎壁部分の日射熱取得量は考慮しませんでしたが、新計算方法では基礎壁の計算が必要になります。
基礎壁の面積は外皮面積に加算します。
なお、土間床外周部の日射熱取得量はゼロとします。
取得日射熱補正係数
従来の詳細計算法は削除されました。
そのため、取得日射熱補正係数を計算する方法としては以下のものがあります。
日除けがある場合
・定数
・簡易的に算出する方法(簡略計算法)
・日除け効果係数と斜入射特性を用いる方法
日除けがない場合
・定数
・日除け効果係数と斜入射特性を用いる方法
日除け効果係数は「日よけ効果係数算出ツール」を用いて求めます。
URL:https://shading.app.lowenergy.jp/
日除けがない場合、天窓の場合の日除け効果係数は1となりますので、斜入射の規準化日射熱取得率の値がそのまま取得日射熱補正係数となります。
規準化日射熱取得率は省エネ基準のテキストに表が用意されています。
日よけ効果係数算出ツールを使用して窓一つ一つを計算するのは非常に手間がかかるので、日除けがある場合は簡略計算法で、日除けがない場合は規準化日射熱取得率から計算するのが現実的ではないかと思います。